一枚の営業許可書から見る青梅の歴史
先日訪れた岩蔵温泉の老舗旅館「儘多屋」さん。
そのロビーには一枚の古い営業許可書が飾られています。
発行されたのは明治17年(1884年)ごろ。
よ~く見てみると、そこに書かれた発行元は「東京府」ではなく、なんと「神奈川県」!
「え、青梅って昔は神奈川県だったの?」
そうなんです。この一枚の紙は、私たちの知らない「もう一つの青梅」の姿と、その激動の時代を今に伝えるタイムカプセルのような存在でした。
今回はこの許可書を道標に、青梅のちょっと意外な歴史を辿る旅に出かけてみましょう。
儘多屋さんは岩蔵温泉唯一の旅館です。
歴史と木のぬくもりが息づく美しい空間は、訪れるだけで心が洗われるようです。
岩蔵温泉が気になる方は、ぜひチェックしてみてください👍✨

青梅が「神奈川県」だった頃
![[画像:儘多屋に残る明治17年の営業許可書]](https://baigo.fun/wp-content/uploads/2025/07/mamadaya20250701-1-1024x576.png)
儘多屋さんの営業許可書に「神奈川県」とあるのは、決して間違いではありません。
明治時代のはじめ、日本が近代国家へと生まれ変わる中で、行政区画はめまぐるしく変わりました。
その過程で、現在の多摩地域(西多摩・南多摩・北多摩)は、まるごと神奈川県に属していた時期がありました。
許可書が発行された明治17年(1884年)当時、青梅はまぎれもなく神奈川県西多摩郡の一部でした。
なぜ青梅は「東京」に引っ越したの?
では、なぜ青梅は神奈川県から東京府(現在の東京都)へといわば「お引越し」をしたのでしょうか?
それは、明治26年(1893年)のこと。
表向きの大きな理由は、首都・東京の人口増加に対応するための「水道問題」でした。
安全で安定した水を確保するため、水源である多摩川の上流域一帯を、東京が直接管理下に置く必要があったのです。
![[画像:自由民権運動演説会の光景]](https://baigo.fun/wp-content/uploads/2025/07/image.png)
しかし、その裏にはもう一つの政治的な理由がありました。
当時、この三多摩地域は、政府に批判的な自由民権運動が非常に盛んな土地柄でした。
そのため、政府としては、首都のすぐ隣に政治的に不安定な地域があることを懸念し、直接管理下に置きたいという思惑もあったと言われています。
住民の想いとは少し違う場所で、首都のインフラ確保と政治的な駆け引きという大きな波に乗り、青梅は東京の一部となりました。
自由民権運動といえば、板垣退助とともに思い出される政治運動ですが、こうした歴史上の活動が、青梅にも影響していたのですね。
「青梅市」が生まれるまで
今でこそ一つの「青梅市」ですが、戦後まではそれぞれが独立した「町」や「村」の集合体でした。
中心には、宿場町として栄えた青梅町があり、その周りには霞村や調布村、さらに山あいには吉野村、三田村、小曽木村、成木村といった、個性豊かな村々が点在していました。
これらの村々は、戦後の昭和26年(1951年)と昭和30年(1955年)の二段階の「昭和の大合併」を経て、現在の広大な青梅市の姿になったのです。
これは、戦後復興と経済成長を目指す国の方針のもと、行政を効率化するために全国的に進められた動きでした。
隣の谷で鳴り響いた銃声「秩父事件」
![[画像:秩父の山]](https://baigo.fun/wp-content/uploads/2025/07/chichibu.jpg)
儘多屋さんが営業許可を得た明治17年(1884年)は、日本史に残る激動の年でした。
青梅から山の向こう、すぐお隣の埼玉県秩父では、近代日本で最大規模の農民蜂起「秩父事件」が勃発したのです。
なぜ農民たちは立ち上がったのか?
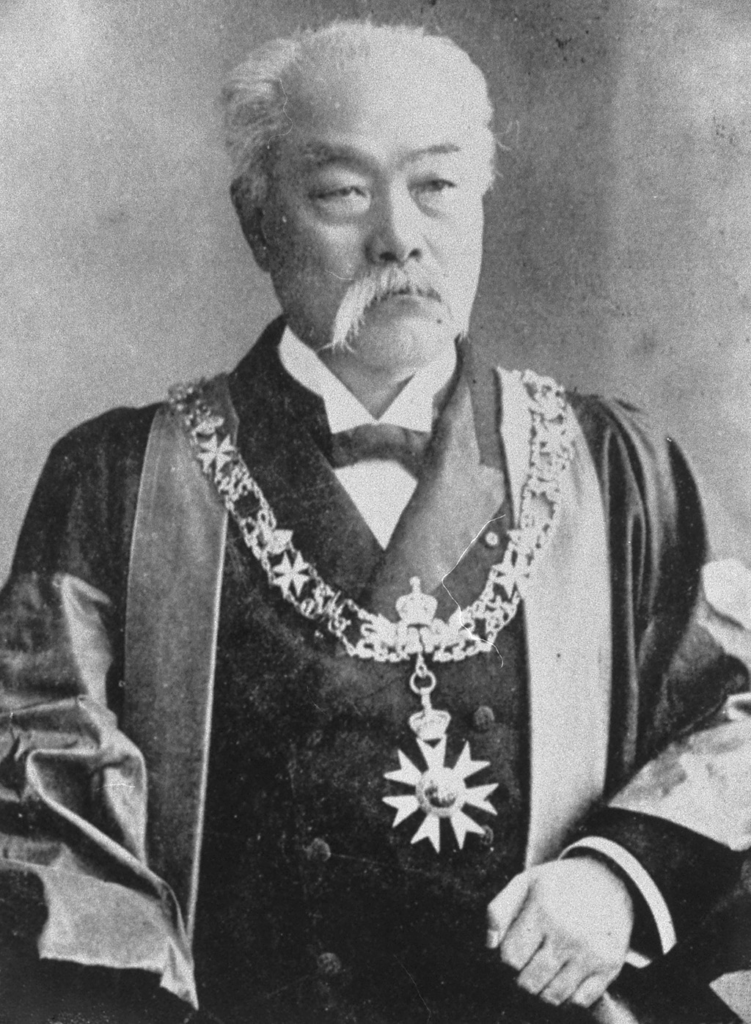
原因は、政府の急進的なデフレ政策「松方デフレ」でした。
それまでのインフレを抑えるための政策でしたが、これにより物価が急落。特に秩父の基幹産業であった生糸の価格が大暴落してしまいます。
借金をして養蚕業を営んでいた農民たちは、収入が激減し、借金だけが残るという地獄のような状況に……。
高利貸しからの厳しい取り立てに耐えかね、先祖代々の土地や家を失う人々が続出しました。
希望を失った農民たちは、ついに武器を手に立ち上がります。
10日間の「戦争」
明治17年10月31日、蜂起した農民たちは「困民党」を名乗り、数千人規模に膨れ上がります。
11月2日には秩父の中心地を占拠し、郡役所に「革命本部」の札を掲げ、一時的に秩父一帯を完全に支配下に置きました。
しかし、近代的な装備を持つ政府の正規軍(陸軍)が投入されると、竹槍や古い猟銃で戦う困民党はなすすべもなく、わずか10日ほどで完全に鎮圧されてしまいます。
指導者たちは死刑になるなど、事件は悲劇的な結末を迎えました。
なぜ青梅では事件が起きなかったのか?
青梅と秩父は、山一つ隔てただけの隣人です。直線距離にしてわずか35〜40km。当時でも徒歩1〜2日の距離でした。
隣の郡で農民が軍隊を組織し、役所を占拠したというニュースは、すぐに青梅にも届き、人々を震撼させたに違いありません。
同じようにデフレで苦しんでいたはずなのに、なぜ青梅では同様の蜂起が起きなかったのでしょうか?
その答えは、経済構造の多様性にありました。
- 秩父: 経済の大部分を「生糸」という一つの産業に頼っていたため、生糸価格の暴落が地域経済全体の致命傷となった。
- 青梅: 伝統的な織物「青梅縞」に加え、首都・東京の建設ラッシュを支える「木材」や「石灰石」といった複数の産業があった。
この「経済の多様性」がクッションの役割を果たしたと言われています。
![[画像:シネマネコさんの外観]](https://baigo.fun/wp-content/uploads/2025/05/cinemaneko-1-1024x576.png)
青梅駅すぐの観光スポット「シネマネコ」さんが青梅織物工業協同組合の旧都立繊維試験場だったように、青梅では織物業が盛んでした。
こうした青梅の織物業も打撃を受けましたが、建設資材の需要が地域経済を支えました。一つの産業がダメになっても、他がなんとか持ちこたえられたのです。
対照的に、秩父では生命線である生糸が絶たれたことで、地域全体が破綻へと向かってしまいました。
明治17年という嵐の年に、儘多屋さんが静かに商いを続けられていたこと自体が、この地域の経済的な強さの証だったのかもしれませんね。
シネマネコさんは昭和レトロな街並みが残る青梅に、新たな文化スポットとして誕生した映画館です。
館内にはカフェスペースもあり、グッドデザイン賞を受賞したおしゃれな施設でコーヒーをいただくこともできます☕✨

まとめ:歴史はすぐそばにある
もう一度、儘多屋さんの営業許可書を思い浮かべてみてください。
一枚の古い紙が、青梅が神奈川県だったという意外な過去や、近代化の波、そして隣で起きた悲劇的な事件の響きまで、私たちに語りかけてくれているようです。
歴史は、博物館や教科書の中だけにあるのではありません。
私たちが普段歩いている道、古い建物、お店に何気なく飾られている一枚の賞状や写真の中に、誰かに発見されるのを待っている物語が眠っています。
青梅を散策する際は、ぜひそんな歴史の痕跡を探してみてください。あなたの知っている街の、全く新しい顔が見えてくるかもしれませんよ。
参考
- 多摩東京移管, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000001/1233/No116(2023.05)2-3.pdf
- 地域の歴史 | 青梅市自治会連合会, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.ome-rengou.jp/contents_detail.php?frmId=5146
- 青梅町 – Wikipedia, 7月 1, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%A2%85%E7%94%BA
- 新町・末広町地区の歴史 – 青梅市自治会連合会, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.ome-rengou.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5092
- 小曾木 – Wikipedia, 7月 1, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9B%BE%E6%9C%A8
- 変貌 – 35.三多摩を東京府に編入 – 国立公文書館, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/henbou/contents/35.html
- 三多摩地域の編入 – 東京, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.tokyo-23city.or.jp/jigyo/kikaku/tenji/r_02/tokyoarchives/documents/3_3tama.pdf
- 小曽木村 – Wikipedia, 7月 1, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9B%BD%E6%9C%A8%E6%9D%91
- 東京府へ移管 – 狛江市役所, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/45,65130,349,2094,html
- 【東京府に編入される】 – ADEAC, 7月 1, 2025にアクセス、 https://adeac.jp/akishima-arch/text-list/d400010/ht050070
- 青梅のあゆみ – 東京都青梅市公式ホームページ, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/2/425.html
- 青梅市文化財ニュース, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/10091.pdf
- 北小曽木~東青梅 – 百街道一歩の道中記, 7月 1, 2025にアクセス、 http://hyakkaido.travel.coocan.jp/narikikaidoufukiagegoekitaosokihigasioume.html
- 秩父事件 – 小海町, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.koumi-town.jp/office2/archives/files/pdf/3c72d05ea953d889c50c705c531d100c6ff3bd8e.pdf
- 秩父事件 – 秩父観光協会, 7月 1, 2025にアクセス、 https://www.chichibuji.gr.jp/chichibujiken/
![[画像:儘多屋さんの営業許可書]](https://baigo.fun/wp-content/uploads/2025/07/mamadaya20250701-1.png)

